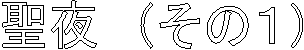
以下の文章は、1988年12月のリュブリャーナ訪問の体験を元に、ある機会に紀行文として書いたものです。
思い入れたっぷりの文章で、今読むと恥ずかしい感じがありますが、これも一応記録の一環ということで、そのまま転載。
事実関係については、「カイロの男たち」(北アフリカ編)同様体験したままで、基本的には旅日記の再構成です。

霧に沈むリュブリャーナ
リュブリャーナ――その響きから受ける印象の通り繊細で美しい、ユーゴスラビア北部にあるこの町を訪れたのは今から10年近く前の年の暮れである。ほどなくこの国は内戦の泥沼へと突き進んでいき、再びぼくがこの町の名を目にしたのはスロベニア共和国の中心であるリュブリャーナが砲撃により破壊されたことを伝える短い記事であった。事実だけを淡々と伝える新聞記事を眺めながら、あの静かに霧に沈む美しい町の記憶をたどったが、その時真っ先に思い浮かんだのは町外れの公園の端に建つ一軒の小さなホテルのことであった。ぼくはこれから机に向い、リュブリャーナのこと、そしてその年の大晦日の夜、静かな時を過ごしたそのホテルのことを書いてみようと思う。読んでくれた誰かが、このホテルを訪れ、無事であることを確かめてきてくれることを願いながら。
南からの夜行列車がリュブリャーナに着いたのは12月30日朝のことであった。年明けにフランクフルトから日本に向かう予定のぼくは、ユーゴ旅行最後の訪問地にこの町を選んだのだ。
駅の案内所で地図を手に入れて町に出た。町は霧に閉ざされていた。始め朝のうちだけかとも思ったが、そうではなく、霧は一日中立ちこめ、濃くも薄くも変わることがない。翌日もまた同じであった。太陽の気配がなく、昼と夜の違いは、薄暗いか暗いかの違いだけであった。ぼくは繁華街を歩き、町のシンボルである三本橋を渡り、城に登り、旧市街を歩き、市場をひやかした。ここまで来ればオーストリアやイタリアの国境はもう近く、街や人の様子にも西ヨーロッパ的な洗練された華やかさが感じられた。しかし、路上に露店が並び、肉を焼く匂いが流れる年末の賑わいの中にあって、僕を包んでいたものはむしろすべてが霧の中に溶けて、そして消えてゆく静寂であった。町の中心に電気会社の高層ビルがあり、その上部は時刻と気温とを交互に示す大きな電光掲示板になっている。歩いていてかなりの寒さを感じていたが、気温はやはりたいていマイナス2度を表示していた。なにしろこの町でたったひとつの高層ビルであり、街角、街角でどうしても目に入る。この町で最も印象に残った光景は、霧の中空に無言でぼんやり浮かぶ−2℃という文字であったかも知れない。
( 以下「聖夜(その2)」 に続く )

年の瀬の賑わい 通りの奥は霧にかすむ