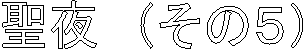
また例のグループが戻ってきた。ひとりだけいる小柄な女の子はもう踊り出さんばかりである。彼らのいろいろな注文に、彼はまじめな表情で律義に応えている。彼らが出て行った後、あれはどこの連中だい、と尋ねると、イタリアーノと言って肩をすくめた。それは彼が初めて見せた自分の表情であったが、僕にはその表情がこの国や彼自身の立場を十分に表しているように思われ胸をつかれた。その後しばらく人の出入りは無く、彼もぼくの向かいのソファーに意識的にそうするのか浅く腰かけ、少しずつ話し出した。
彼は23歳だと言った。レセプションのカウンター越しに話すだけだと、ヨーロッパの男は日本人には大人に見える。彼の戸とも初め自分より年上だと思っていたのだが、話をしてみるとやはりその位の年かなとも思う。ぼくはウイスキーを飲み続け、彼との会話を続けた。大晦日の夜は静かに更けていった。一度だけ酔っ払ったじいさんがドアを開けて何かわめいていたが、彼がなだめて追い返した。こういう闖入者もこの夜の静寂を印象づけるものであった。
10時を回ってぼくは立ち上がり、握手で彼に別れを告げた。最後も彼はホテルマンらしくドアを開けて送り出してくれた。ぼくは霧の夜の中に入っていった。

駅の待合室は列車を待つ人というよりは、さ迷いこんできた街の酔っ払いであふれんばかりで、何をしたのか解らないが、公安係が来てそのうちのひとりを連れてゆくという騒ぎもあった。出発の時間になった。ベオグラードを昼出てきた列車はすでに入選している筈であったが、なかなか見つけられない。列車は少し離れたホームの、しかも線路を一つまたぎこした向こうというとんでもないところにひっそり停車していた。こんな日に国境を超える者などそういないのか、車内は人気がなく、何度も確かめて乗り込んだ。
程なく列車はゆっくりと動き出した。ぼくは後ろに流れる光を眺めながら、霧の町リュブリャーナを、丘の上に立つホテルベルビュウを、そして今でもレセプションにいるのであろう男の横顔を思い出していた。間もなく日付が変わり、新しい年を迎えた。
(終わり)

霧に包まれるリュブリャーナ旧市街